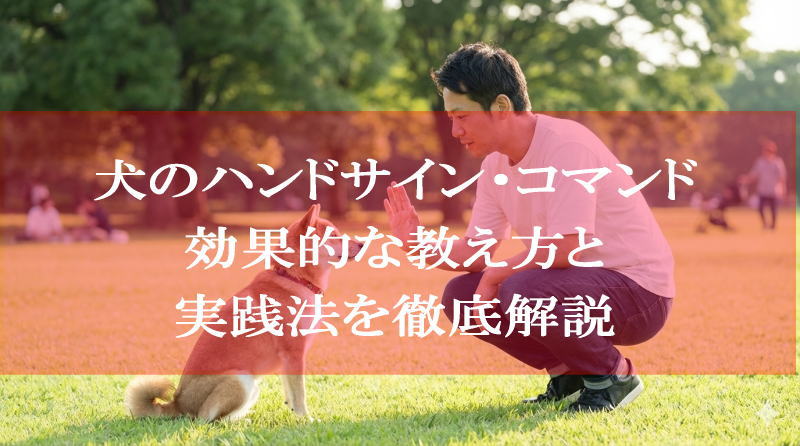「ドッグランで呼んでも、愛犬に声が届かない」
「シニアになって、耳が遠くなってきたみたい」
「ドッグランで声が届かない」「愛犬の耳が遠くなった」とお悩みではありませんか?
そんな時に役立つのが、声を使わず指示を出す「ハンドサイン」です。
これを使えば、騒がしい場所やシニア犬相手でもスムーズに意思疎通ができます。
「難しそう」と感じるかもしれませんが、正しい手順なら誰でも簡単に習得可能です。
この記事では、ハンドサインの基本コマンドから効果的な教え方までを解説します。
愛犬との絆を深める新しいコミュニケーションを始めましょう。
犬にハンドサインでコマンドを教えるメリット

ハンドサインは、単なる「芸」ではありません。
日常生活や緊急時に役立つ、実用的なスキルです。
そもそも犬は、聴覚以上に視覚情報へ敏感に反応する動物なのです。
ここでは、習得することで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
騒がしい場所でも指示が通る
外出先では、様々な環境音が溢れています。
車の走行音や、他の犬の鳴き声で指示がかき消されることもあるでしょう。
そんな時、大声で叫ぶ必要はありません。
ハンドサインなら、視線が合えば確実にメッセージが届きます。
静かに、そしてスマートに愛犬をコントロールできます。
とっさの危険回避にも役立つ、命を守るツールと言えます。
高齢犬の聴力低下にも対応できる
犬も年齢を重ねれば、耳が遠くなるのが自然です。
名前を呼んでも反応がなくなり、寂しく感じる時が来るかもしれません。
しかし、ハンドサインを覚えていれば大丈夫です。
聴力が衰えても、目が見えていればコミュニケーションは途絶えません。
愛犬がシニア期を迎えても、安心して意思疎通を続けるための備えになります。
犬との絆が深まる
ハンドサインを受け取るには、犬が飼い主を見る必要があります。
つまり、自然とアイコンタクトの回数が増えるのです。
「ご主人は次、何をするのかな?」
そんな風に、愛犬は飼い主の一挙手一投足に注目するようになります。
お互いに見つめ合う時間が増え、信頼関係はより強固なものになるでしょう。
犬のハンドサインコマンド・基本の種類

ハンドサインに、「これ以外はダメ」という厳格な決まりはありません。
ですが、犬にとって分かりやすく、一般的に使われている型があります。
ここでは基本となる4つのサインを見ていきましょう。
これらをマスターすれば、日常の困りごとの多くは解決します。
おすわりのハンドサイン
まずは基本の「おすわり」から始めましょう。
犬の顔を自然に上向かせる動きを利用します。
- 手のひらを上に向け、下からすくい上げるように動かす
- または、人差し指を一本立てて上に挙げる
視線が上がると、バランスを取るために自然と腰が下がります。
犬の体の構造を利用した、理にかなったサインです。
伏せのハンドサイン
「伏せ」は、おすわりとは対照的に視線を下げる動きです。
落ち着かせたい時に有効なコマンドです。
- 手のひらを下に向け、胸の高さから地面へ下ろす
- 人差し指で地面を指差す
勢いよく振り下ろすと、犬が威圧感を感じてしまうことがあります。
ゆっくりと、「ここだよ」と教えるように下げてみてください。
待てのハンドサイン
「待て」は、犬の行動を静止させる重要な合図です。
人間同士でも使う「ストップ」のジェスチャーを使います。
- 手のひらを相手に向け(パーの形)、腕を前に突き出す
- 警察官が交通整理で車を止めるイメージ
視覚的なインパクトが強く、犬にも意味が伝わりやすい動きです。
動いてはいけないという境界線を、手で示すイメージです。
おいでのハンドサイン
「おいで」は、愛犬を呼び戻すための楽しいサインです。
歓迎の意を表すよう、大きく動くのがコツです。
- 両手を広げて、ハグをするようなポーズをとる
- 片手で「こっちにおいで」と手招きをする
- 自分の太ももをポンポンと叩く
笑顔で行うことで、犬は「行くと良いことがある!」と感じ取ります。
遠くからでも見えるよう、オーバーリアクション気味がおすすめです。
犬にハンドサインのコマンドを教える方法

形を覚えたら、いよいよ実践トレーニングです。
犬はいきなりハンドサインだけを見せられても理解できません。
「言葉」と「動き」をつなげる作業が必要です。
誰でも成功しやすい、3つのステップで進めていきましょう。
①声のコマンドと同時に使う
まずは、犬が既に知っている言葉の力を借ります。
「おすわり」という声掛けと完全に同時に、ハンドサインを出してください。
ここでのポイントは、タイミングをずらさないことです。
「この言葉」=「この手の動き」だと、犬の頭の中でリンクさせます。
何度も繰り返し、セットで印象付けましょう。
②徐々に声を減らしていく
セットでの指示に慣れてきたら、次の段階です。
ハンドサインを出した直後、一瞬遅らせてから声をかけます。
もし、声が出る前に犬が反応し始めたら大成功です。
徐々に声のボリュームを絞ったり、声を出す頻度を減らしたりしてみます。
最終的には、無言のサインだけで動けるように導きます。
③成功したらすぐ褒める
トレーニングの鍵は、成功体験の積み重ねです。
ハンドサインで正しく動けた瞬間、大げさなくらい褒めてあげましょう。
- 大好きなおやつをあげる
- 「よし!」「すごいね!」と高い声で褒める
- 体を優しく撫でる
「サインを見れば良いことがある」と学習すれば、習得は早くなります。
正解した瞬間のご褒美が、何よりのモチベーションになります。
自宅で学べるしつけ講座
ハンドサインコマンドを教える時の注意点

ハンドサインは便利ですが、教え方を誤ると犬が混乱してしまいます。
スムーズに覚えてもらうために、気をつけるべきポイントがあります。
特に以下の2点は、必ず意識してください。
サインは一貫性を持たせる
最も大切なのは、サインの形を統一することです。
お父さんとお母さんで違う動きをしていては、犬は何が正解か分かりません。
「おすわりは手のひらを上」など、家族全員でルールを決めましょう。
また、その日の気分で動きを変えるのも厳禁です。
いつでも同じサインを出すことが、犬への思いやりです。
大きくわかりやすい動きにする
犬にとって見えにくいサインは、存在しないのと同じです。
特に屋外や距離が離れている場合、指先の細かい動きは伝わりません。
腕全体を大きく動かし、シルエットで伝える意識を持ちましょう。
夜間や背景によっては、白い手袋をして目立たせるのも効果的です。
「犬からどう見えているか」を常に想像してみてください。
まとめ:犬のハンドサインコマンドは正しい教え方で必ず覚える

犬へのハンドサインについて、実践法を解説しました。
声が届きにくい環境や、シニア期のコミュニケーションに欠かせないスキルです。
難しく考えず、遊びの延長で取り組んでみてください。
| ステップ | 成功のコツ |
|---|---|
| ステップ1 | 声とサインを同時に出して関連付ける |
| ステップ2 | 徐々に声を小さくし、サイン主体にする |
| ステップ3 | 出来たら即座に褒めて定着させる |
愛犬は、あなたの動きをしっかりと見ています。
正しい手順で教えれば、必ず応えてくれるはずです。
今日から少しずつ、愛犬との新しい会話を始めてみませんか?
もし自己流でうまくいかない時は、プロの力を借りるのも賢い選択です。
愛犬との絆がさらに深まることを願っています。