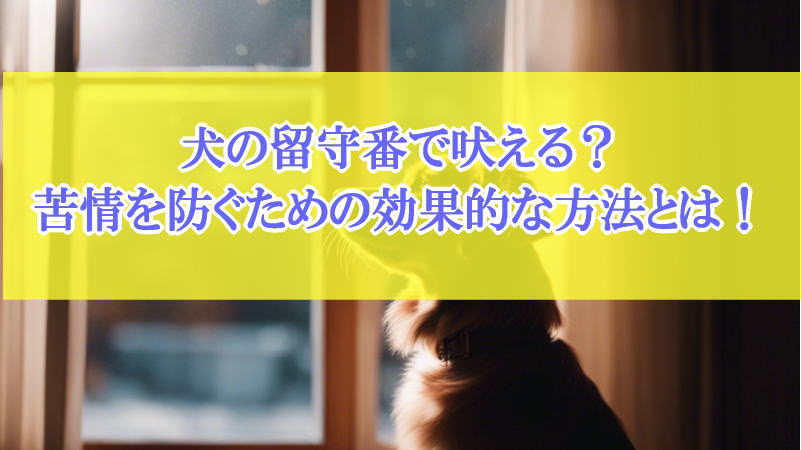仕事から帰宅したら、ポストに「騒音について」という手紙が。
それを見た瞬間、血の気が引く思いをしませんでしたか?
「仕事中も犬が吠えていないか気が気じゃない…」
そんな悩みを抱える飼い主さんは、あなただけではありません。
留守番中の吠えは深刻ですが、正しい手順を踏めば必ず解決の糸口は見つかります。
近所トラブルになる前に、今日からできる対策を一緒に見ていきましょう。
犬が留守番中に吠える原因とは?

やみくもに叱っても、吠えは止まりません。
まずは「なぜ吠えているのか?」を知ることが解決への近道です。
犬が吠えるのには、必ず以下の3つのような理由があります。
- 独りぼっちが怖い(分離不安)
- 体力が余って退屈している
- 外の音に反応して家を守っている
分離不安による寂しさ
犬はもともと、群れで生活する動物です。
そのため、飼い主さんがいなくなるとパニックになる子がいます。
これが「分離不安」と呼ばれる状態です。
「行かないで!」「早く帰ってきて!」
そう訴えるために、枯れるまで吠え続けてしまうのです。
特に、普段から飼い主さんにべったりな子は要注意です。
退屈やストレスの発散
健康な犬にとって、狭い部屋での留守番は退屈そのものです。
体力が有り余っていると、そのエネルギーが「吠え」に向かいます。
また、長時間ケージに入っているストレスもあるでしょう。
「ここから出して!」「遊んでよ!」
そんな要求の意味で吠えているケースも非常に多いです。
外の物音への反応
あなたの愛犬は、チャイムや足音に敏感ではありませんか?
犬は聴覚が優れているため、外の気配を敏感に察知します。
これは「怪しいやつが来たぞ!」という防衛本能です。
番犬としては優秀ですが、集合住宅では騒音トラブルの元になります。
特に、神経質な性格の犬に多く見られるパターンです。
犬の留守番中の吠えで苦情が来た時の対応

もし苦情が来てしまったら、何よりも「初動」が肝心です。
対応を間違えると、そこに住み続けられなくなるリスクもあります。
焦る気持ちを抑えて、以下の手順で誠実に対応しましょう。
- 菓子折りを持って直接謝罪に行く
- 対策を始めていることを伝える
- その後の経過を報告する
まずは謝罪と状況説明
苦情の手紙や連絡を無視するのは絶対にNGです。
まずは相手のお宅へ伺い、誠心誠意謝りましょう。
「ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません」
この一言があるだけで、相手の怒りは大きく鎮まります。
「飼い主は問題を認識している」と分かってもらうことが重要です。
改善の意思を伝える
謝罪だけで終わらせず、具体的な行動を示しましょう。
「専門の教材でしつけを始めました」
「防音マットを敷いて対策しました」
このように伝えると、相手も「そこまでやるなら待ってみよう」と思えます。
本気で解決しようとする姿勢を見せることが、信頼回復のカギです。
犬が留守番中に吠えるのを防ぐ対策

では、具体的にどうすれば吠えは止まるのでしょうか?
プロも実践する、効果的な3つの対策をご紹介します。
どれも今日から始められるものばかりです。
出かける前に運動で疲れさせる
最もシンプルかつ効果的なのが、事前の運動です。
留守番の前に、少し長めの散歩やボール遊びをしてみてください。
心地よい疲れがあれば、犬は留守番中に眠って過ごします。
吠えるための体力を、遊びで使い果たさせておくのです。
朝の15分早起きが、一日の平穏を作ります。
一人で遊べるおもちゃを用意
留守番中、愛犬が夢中になれる「仕事」を与えましょう。
おすすめは、中におやつを詰められる知育玩具です。
おやつを取り出すのに頭と時間を使うため、吠える暇がなくなります。
「留守番=おいしいおやつタイム」と覚えさせるのがコツです。
ただし、壊れにくい丈夫なものを選んでくださいね。
短時間の留守番から練習する
いきなり長時間の留守番は、犬にとってハードルが高すぎます。
まずはゴミ出し程度の、5分~10分から練習しましょう。
「飼い主はいなくなっても、必ず帰ってくる」
この安心感を少しずつ刷り込んでいくことが大切です。
出かける時も帰った時も、大袈裟に構わず「さりげなく」が鉄則です。
自宅で学べるしつけ講座
留守番の吠え対策に役立つグッズ

しつけと同時に、環境を整えることも非常に有効です。
便利なグッズを使えば、飼い主さんの負担も軽くなります。
導入を検討したいアイテムを整理しました。
| グッズ | 効果 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ペットカメラ | 状況確認 | 原因が分からない人 |
| 防音カーテン | 音の遮断 | 外の音に吠える人 |
| 吸音マット | 振動吸収 | 階下への配慮が必要な人 |
ペットカメラで様子を確認
敵を知るには、まず現状把握からです。
スマホで見れるカメラがあれば、吠えるタイミングが分かります。
「雷の音?」「来客?」「寂しさ?」
原因が特定できれば、対策もピンポイントで行えます。
最近は数千円で買えるものも多いので、ぜひ導入してみてください。
防音グッズの活用
物理的に音を漏らさない工夫も、苦情対策には欠かせません。
窓には防音カーテン、床には厚手のコルクマットなどが有効です。
これらは犬の声を小さくするだけではありません。
外の騒音を遮断し、犬が落ち着ける環境を作る効果もあります。
「やれる対策は全てやっている」という事実は、謝罪時の説得力にもなります。
まとめ:犬の留守番中の吠えは対策次第で苦情を防げる

留守番中の吠えは、放置しても自然には直りません。
しかし、諦める必要もありません。
最後に、今日から意識すべきポイントを復習しましょう。
- 原因(寂しさ・退屈・警戒)を見極める
- 苦情が来たらすぐ謝り、改善策を伝える
- 出かける前の運動で疲れさせる
- 「必ず戻る」という安心感を教える
- 防音グッズで物理的な対策も行う
愛犬との生活を守れるのは、飼い主であるあなただけです。
一人で悩まず、信頼できる教材やプロの手を借りるのも賢い選択ですよ。
近隣に気を使わない、穏やかな毎日を取り戻しましょう。