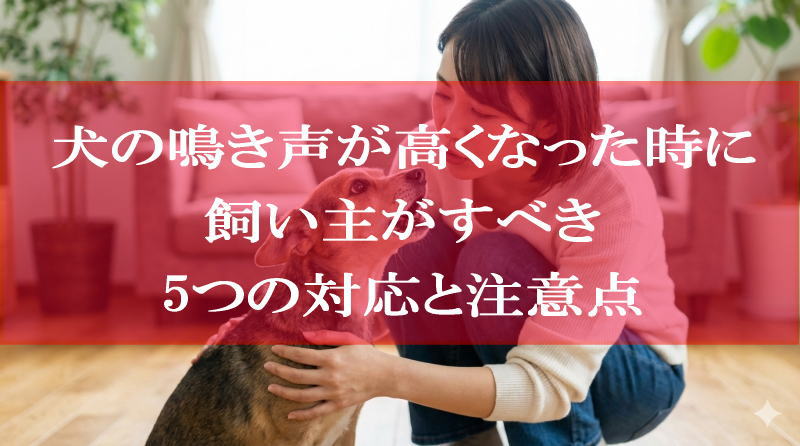「あれ?急に声が高くなった?」
愛犬の鳴き声がいつもと違うと、ドキッとしてしまいますよね。
どこか痛いのか、それともただの甘えなのか。
言葉を話せない愛犬だからこそ、その変化が不安になるのは当然です。
実は、犬の声が高くなるのには「心の叫び」と「体のSOS」の2種類があります。
この記事では、その見極め方と、飼い主さんがとるべき行動を整理しました。
焦らず一つずつ確認して、愛犬の不安を取り除いてあげましょう。
犬の鳴き声が高くなった原因とは?

なぜ急に声のトーンが変わったのでしょうか。
犬が高い声を出すときは、感情や感覚が鋭くなっている証拠です。
大きく分けて3つのパターンがあるので、愛犬の様子と照らし合わせてみてください。
興奮や甘えの表現
まず考えられるのは、気持ちが高ぶっているケースです。
「おやつだ!」「散歩に行ける!」という喜びが爆発すると、声は自然と高くなります。
また、飼い主さんに甘えたい時に出す「クゥーン」という鼻声も高いトーンになりがちです。
尻尾を振っていたり、目がキラキラしていれば、ポジティブな理由なので心配はいりません。
不安やストレスを感じている
次に、精神的なSOSの場合です。
犬は不安や恐怖を感じると、助けを求めるように高い声を出します。
苦手な音が聞こえたり、留守番で寂しさを感じたりしていませんか?
この場合、耳を後ろに伏せていたり、体が小刻みに震えていることが多いです。
見えないストレスが、愛犬を追い詰めている可能性があります。
体調不良や痛みのサイン
一番見逃してはいけないのが、体の痛みです。
どこかに激痛が走った時、犬は「キャン!」と鋭く高い悲鳴を上げます。
また、体に違和感がある時も、細く高い声で鳴き続けることがあります。
普段おとなしい子が急に高い声で鳴くなら、緊急性が高いサインかもしれません。
犬の鳴き声が高くなった時に確認すべきポイント

原因を絞り込むために、もう少し詳しく観察してみましょう。
病院に行く際にも、この情報は非常に役立ちます。
いつから変化したか
「いつ」声が高くなるかに注目してください。
特定のタイミングなら、原因は環境にあることが多いです。
- 飼い主が出かける準備を始めた時
- チャイムが鳴った時や、外で工事音がする時
- 夜、寝静まった後に突然鳴き出す時
逆に、一日中ずっと声が高い場合は、体調の変化を疑う必要があります。
他に行動の変化がないか
鳴き声以外の「動き」も重要なヒントです。
歩き方がぎこちなかったり、抱っこを嫌がったりしていませんか?
また、意味もなくウロウロ歩き回る、壁に向かって鳴くといった行動も要注意です。
これらは、関節の痛みや、脳の老化による変化かもしれません。
食欲や元気の有無
わかりやすい健康のバロメーターは、やはりご飯と元気です。
声が高くても、ご飯を完食しておもちゃで遊ぶなら、心の問題(甘えや不安)が濃厚です。
しかし、ご飯を残す、うずくまって動かないといった場合は危険信号です。
何らかの病気が隠れている可能性が非常に高いです。
犬の鳴き声が高くなった時にすべき5つの対応

では、実際に声が高くなった時、どう対応すればよいのでしょうか。
慌てず、以下の5つのステップを順に試してみてください。
①まず落ち着いて観察する
飼い主さんが焦ると、犬は余計に不安になります。
まずは深呼吸をして、冷静に愛犬を観察してください。
「何を見ているか」「どこを触ると嫌がるか」をチェックします。
可能であれば、スマホで動画を撮っておくと、後で専門家に見せる時に役立ちます。
②環境の変化がないか確認する
最近、愛犬の周りで変わったことはありませんか?
| 環境の変化 | 犬への影響 |
|---|---|
| 部屋の模様替え | 自分の居場所がわからず不安 |
| 家族の外出時間増 | 分離不安によるストレス |
| 新しい家電の導入 | 聞き慣れない高周波音への恐怖 |
人間には些細なことでも、犬にとっては大きなストレス源になります。
③ストレス要因を取り除く
原因がわかったら、できるだけそれを取り除いてあげましょう。
外の音が怖いなら窓を閉める、留守番が寂しいならテレビをつけておくなどです。
環境を少し変えるだけで、驚くほど落ち着くこともあります。
④スキンシップで安心させる
不安や恐怖で声が高くなっている時は、飼い主さんの優しさが一番の薬です。
「大丈夫だよ」と低い声で話しかけながら、ゆっくり背中を撫でてあげてください。
安心感を与え、興奮を鎮めることができます。
ただし、ただのワガママで吠えている時に構いすぎると、悪化するので見極めが大切です。
⑤改善しなければ動物病院へ
環境を整えても、優しく接しても治まらない場合。
あるいは、触ると痛がる様子がある場合は、迷わず病院へ行ってください。
「様子を見よう」と先延ばしにするのが一番のリスクです。
病気が原因なら、早期発見が愛犬の命を救います。
鳴き声が高くなった犬で注意すべき病気

「ただの加齢かな?」と思っていたら、実は病気だったというケースは少なくありません。
特に以下の3つは、声の変化として現れやすい病気です。
- 認知症:夜中に単調な高い声で鳴き続ける
- 関節炎・ヘルニア:動いた瞬間に「キャン!」と悲鳴を上げる
- 甲状腺機能低下症:声がかすれたり、トーンが変わったりする
愛犬からのサインを見逃さないでください。
少しでも「おかしいな」と感じたら、獣医師に相談するのが正解です。
何もなければそれで安心できますし、早期発見できれば治療の選択肢も広がります。
まとめ:犬の鳴き声が高くなったら原因を探り適切に対応しよう

犬の鳴き声が高くなるのは、飼い主さんへの大切なメッセージです。
最後に、対応のポイントを振り返りましょう。
- 甘えか、不安か、痛みか、まずは冷静に観察する
- 環境の変化やストレス要因がないかチェックする
- 痛みや行動の異常があれば、すぐに動物病院へ
病気ではなく、不安や関係性の問題であれば、しつけ方を見直すことで解決できることも多いです。
愛犬の「声」に耳を傾け、正しい対応をしてあげてくださいね。
あなたの理解と行動が、愛犬の笑顔と安心につながります。