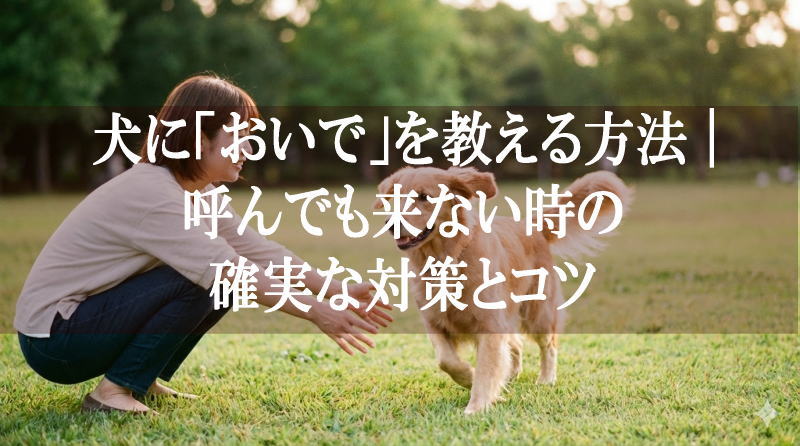愛犬の名前を呼んでも無視されると、寂しいだけでなく不安になりますよね。
ドッグランで遊びに夢中な姿を見て「帰れるかな…」と冷や汗をかくことも。
万が一の脱走や災害時を考えると、呼び戻しは命綱とも言えるスキルです。
実は、呼んでも来ない原因の多くは「教え方」と「誤解」にあります。
この記事では、犬においでを教える方法と、来ない時の具体的な対策を解説します。
今日からできる練習で、愛犬が喜んで飛んでくる関係を目指しませんか?
犬に「おいで」を教える方法・基本ステップ

呼び戻しの訓練は、愛犬の安全を守るための最優先事項です。
いきなり外で実践するのではなく、まずは静かな室内から始めましょう。
成功体験を積み重ねるための、基本の3ステップを紹介します。
①短い距離から始める
最初から遠く離れて呼んでも、犬には声が届きにくいものです。
まずは「手を伸ばせば鼻先に触れる距離」からスタートしてください。
お互いの表情がしっかり見える距離感が、安心感を生みます。
犬がふとこちらを見た瞬間に、練習を始めるのが成功のコツです。
確実にできる距離で「できた!」という自信をつけさせましょう。
②名前を呼んでからおいでと言う
犬に合図を送るときは、まず名前を呼んで「私を見て」と伝えます。
視線が合ったら、明るくはっきりした声で「おいで」と言いましょう。
この時のコマンドは「来い」「カム」など、家族内で統一するのが鉄則です。
人によって言葉が違うと、犬は何をすれば正解なのか混乱してしまいます。
楽しそうな声色を使うと、犬もワクワクして反応しやすくなります。
③来たらすぐに褒める
犬が足元まで来たら、間髪入れずに全力で褒めちぎりましょう。
おやつをあげたり、大袈裟なくらい撫でたりして歓迎します。
「ここに来ると最高に良いことがある」と脳に刷り込むのです。
ポイントは、来てから1~2秒以内にご褒美を与えること。
時間が空いてしまうと、何に対して褒められたのか伝わりません。
犬に「おいで」を教える方法で押さえるべきコツ

手順自体はシンプルですが、定着させるには少し工夫が必要です。
犬の学習心理をうまく利用すれば、トレーニングの速度は格段に上がります。
楽しみながら続けるために、以下の3つのコツを意識してみましょう。
おいで=良いことと覚えさせる
「おいで」という言葉が、犬にとって魔法の言葉になるようにします。
呼ばれたら美味しいおやつが貰える、大好きなおもちゃで遊べる。
そんなポジティブな期待感を持たせることが何より重要です。
日頃から用事がなくても呼び、褒めるだけの「ボーナスチャンス」を作ります。
嬉しい予感がすれば、犬は喜んで飼い主の元へ駆け寄るようになります。
失敗しても叱らない
呼んでも無視されたり、来るのが遅かったりしてもイライラしてはいけません。
もし遅れて来た犬を叱ってしまうと、犬はどう思うでしょうか?
「せっかく戻ったのに怒られた」と学習し、次からもっと来なくなります。
戻ってきた事実は必ず褒め、来ない時は静かに無視をするのが正解です。
感情的にならず、淡々とルールを守ることが信頼への近道です。
少しずつ距離を伸ばす
目の前での呼び戻しが完璧になったら、少しずつレベルを上げます。
1メートル、2メートルと距離を伸ばし、次は部屋をまたいで練習します。
最終的には、姿が見えない場所からでも声だけで反応できるのが理想です。
環境を変える際は、以下の順序で難易度を調整しましょう。
- 静かなリビングで距離を離す
- テレビをつけて少し雑音がある状態で練習
- リードをつけたまま、安全な庭へ出る
急に難しい環境にすると失敗しやすいため、スモールステップを心がけてください。
犬に「おいで」を教えても来ない原因

一生懸命教えているのに成果が出ない場合、犬なりの理由があります。
「なぜ来たくないのか」を知ることで、解決の糸口が見えてきます。
よくある3つの原因を確認し、愛犬の気持ちに寄り添ってみましょう。
過去に嫌なことがあった
「おいで」と呼ばれて行った先で、嫌なことをされた経験はありませんか?
お風呂に入れられた、爪切りをされた、ハウスに閉じ込められたなどです。
犬は記憶力が良いため、「呼ばれる=嫌なことの合図」と警戒しています。
この誤解を解くには、呼ばれても嫌なことは起きないという上書き保存が必要です。
苦手なケアをする時は呼び戻しを使わず、飼い主から迎えに行きましょう。
他に興味があるものがある
散歩中や公園では、犬にとって魅力的な誘惑がたくさんあります。
他のワンちゃん、地面の匂い、ボール遊びなどに夢中な状態です。
この時、飼い主の魅力が外部の刺激に負けてしまっていると言えます。
興奮している最中に呼んでも、声は耳に入りません。
まずは刺激の少ない場所に戻り、飼い主に注目させる練習からやり直しましょう。
練習不足で定着していない
そもそも、まだ言葉の意味を完全に理解していない可能性もあります。
「家ではできるけど外では無理」なのは、応用力がついていない証拠です。
犬にとって場所が変われば、それは全く新しいシチュエーションです。
家の中だけでなく、様々な場所で反復練習を行い、定着度を高めましょう。
完全に覚えるまでは、リードを離さずコントロールできる環境を守ってください。
| 原因 | 犬の心理状態 | 解決へのアプローチ |
|---|---|---|
| 嫌な記憶 | 行くと捕まるかも… | 良いことだけ起きる練習を増やす |
| 興味の分散 | あっちが楽しそう! | 刺激の少ない場所へ戻る |
| 練習不足 | 何て言ったの? | 場所を変えて反復練習する |
呼んでも来ない犬への確実な対策

どうしても来ない場合には、言葉以外の補助や道具の活用が効果的です。
ただ待つだけでなく、環境を整えて「成功せざるを得ない状況」を作ります。
ここでは、プロも実践する確実性の高い対策を2つ紹介します。
ロングリードを使って練習する
外での練習には、10メートルほどのロングリードが必須アイテムです。
呼んでも反応がない時に、リードを軽くクイクイと引いて合図を送ります。
「呼ばれたら必ず飼い主の元へ行く」という行動を物理的にサポートするのです。
自分から来たように見せかけて、到着したら大いに褒めてあげましょう。
ただし、強く引っ張りすぎると首を痛めるので、あくまで誘導に使います。
おやつのレベルを上げる
外の誘惑に勝つためには、報酬(ご褒美)の価値を上げるのが手っ取り早いです。
いつものドライフードではなく、茹でたササミやチーズなどを用意します。
「戻ればとびっきりのご馳走がもらえる!」と分かれば、犬の目の色は変わります。
これをおやつで釣るのではなく、来た後のサプライズとして与えるのがポイント。
「飼い主のところに行けば損はしない」と強く印象付けましょう。
まとめ:犬に「おいで」を教える方法は根気強く続けることが大切

犬に「おいで」を教えるのは、一朝一夕で完成するものではありません。
しかし、正しい手順で信頼を積み重ねれば、必ず伝わるようになります。
最後に、今回の重要ポイントをおさらいしましょう。
- まずは近距離で「できた!」という自信をつける
- おいで=楽しいこと、というポジティブな印象を作る
- 失敗しても叱らず、成功した時だけ盛大に褒める
- 来ない原因を理解し、おやつや環境を見直す
呼び戻しができれば、ドッグランでも安心して遊ばせてあげられます。
何より、愛犬を危険から守るための最強の命綱になります。
もし自己流で行き詰まったら、プロの教材やトレーナーに頼るのも賢い選択です。
焦らず楽しみながら、愛犬との絆を深めていってくださいね。